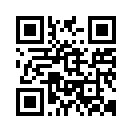2015年11月25日
横浜・伊勢佐木町 物語<86>
イセザキモール全体が音楽&映像タウンと化す…!?
かつての “はまっパレ!” は伊勢佐木町の最西端となる七丁目を突き抜けて、
さらに1キロメートル近く足を延ばした蒔田公園が最終地点だった。
イセザキの中心よりもかなり離れたスポットまでパレードがなされていたのだが、
そんな状況下でもゴールにたどり着くまでのコースには沿道に人垣ができていた。
だが、時代とともにレジャーが多様化してきたこともあってか、
“はまっパレ!” の集客そのものが最盛期の半分以下となった。
そのうえ一大繁華街だった伊勢佐木町のブランド力低下が
ビッグイベントの観客者数減少に拍車をかける。
このように最近の “はまっパレ!” の摸様を垣間見るだけでも、
この街の地盤沈下はもはや隠しようもない。
横浜市が誇る最大のイベントとはいえ、
四丁目を過ぎたあたりから目に見えて聴衆の数は少なくなっていく。
その昔、市街地から離れた蒔田公園までぎっちりと人の波で埋め尽くされていた
ころとは雲泥の違いだ。
こうした現状に危機感を募らせたのか、
伊勢佐木町の再生・活性化に向けて新たな取り組みがスタートした。
とりわけ、過去の成功体験をもっていない若者は現況を直視できる。
華やかだったころの呪縛からなかなか解き放すことができない年嵩の大人たちと違い、
彼らには捨てがたい “遺産” があるわけでない。
こうして若者が中心となり、街に活気を植えつける試みが近年胎動しつつあるのだ。
また前述のごとく、かつての賑わいが肌に染みついている大人たちも、
この土地に根を張る遺伝子を受け継ごうと重い腰を上げた。
さらには名門復活に手を差しのべるのは地元の人間だけではない。
この日の “はまっパレ!” にて2年連続で伊勢佐木町チームのフロートに乗り、
およそ4キロメートルの道のりを、声をからして新バージョンの 「伊勢佐木町ブルース」
を歌いつづける若手3人組ミュージシャンJOHNLOSは他都県の出身だ。
彼らは、なんとかこの街が甦ってほしいと願い、“よそ者” でありながらも
今から40年ほど前にここから誕生した名曲を自ら現代風にアレンジして熱唱する。
そしてまた、伊勢佐木町は我が国の映画産業が巣立った元祖 “映画の街” でもある。
ここ数年で映像の世界もアナログからデジタルへと急速に切り替わっていったが、
撮影・映写の仕組みがどう変わろうと 「映画の街という遺伝子」 がそう簡単に
組み換えられることはない。
それを裏づけるような取り組みも、JOHNLOSと同様に伊勢佐木町が地元ではない
都市プランナー櫻井淳の手で実験的にスタートした。
こんな形で若い世代と円熟した世代、そして地元の人間と外部の人間、それらが
ほどよく調和し、名門復活に向けて新しい “まちづくり” がなされようとしている。
その中心テーマはあらためて強調するが 「音楽と映像」 が主体となる。
それは伊勢佐木町のルーツともいうべき要因であって永遠に閉ざされることはない。
賑やかだった時代からこの街には音楽が鳴り響く。
国内最大級のレコード店だったヨコチクの店頭では多くの歌手が新曲をアピールし、
それがヒット曲を生む原動力となった。
「伊勢佐木町ブルース」 の青江三奈をはじめとして 「よこはま たそがれ」 の五木ひろし、
「ふりむけばヨコハマ」 のマルシアなど枚挙にいとまがない。
また横浜市出身の大御所、美空ひばりもよくヨコチクを訪れた。
こうして “ヒット曲の聖地” と呼ばれた伝説のレコード店もここ伊勢佐木町に存在した。
さらには二人組ボーカリスト 「ゆず」 がこの街からブレークしたのも記憶に新しい。
そんな、音楽と縁のある街という要因はこれからも大切にしていきたいものである。
一方の映像も同様だ。
その昔、伊勢佐木町には数多くの映画館が立ち並んでいて、
我が国最強の映像タウンだった。
横浜は神戸や長崎に勝るとも劣らない大きな港町だけあって舶来の文化が
真っ先に上陸、映画用のフィルムも例外ではなかった。
上陸後それがいち早く届けられる最たる場所が伊勢佐木町であり、ここでフィルムの
入った袋の封を切ることから 「封切」 という映画用語がこの街から生まれたほどである。
このように、音楽と映像はこの街にとって切っても切れないファクターだ。
それらを中軸とした 「新たなまちづくり」 が、今まさに始まろうとしている――。
< 了 >

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at
01:16
│Comments(0)
2015年11月24日
横浜・伊勢佐木町 物語<85>
この街に深く根を下ろした 「賑わい」 という遺伝子
長い間ここ伊勢佐木町でレコード店を経営するなど音楽活動に関わってきた
人間だからこそ、この街への思い入れが人一倍強いのか、全出場チームのなかでも
ひときわ華やかに見えた 「イセザキモール1~7st.&横浜マツザカヤ」 のフロートは、
伊奈正明の目の前を通りすぎて伊勢佐木町四丁目へと突き進んでいった。
このように大掛かりなフロートを採用してチームを編成している企業・団体をはじめ、
全部で50組近くがエントリーしたこの “はまっパレ!” は今大会で55回目となる。
第1回目からずっと参加しているという 「神奈川県警察音楽隊」 が隊列の先陣を切り、
最終組となる 「横浜市消防音楽隊」 までの総勢48組が趣向を凝らした一芸を
沿道の聴衆に披露する。
参加チームはこれらのほかに、横浜商工会議所、神奈川大学、横浜ベイスターズ、
横浜高島屋、相鉄ジョイナス、日産自動車、キリンビール、崎陽軒など、
ここ港ヨコハマにゆかりのある団体や企業ばかりである。
そのうち伊勢佐木町チームのように、
きれいにドレスアップされたフロートでパレードに臨んでいるのは10組近くにのぼる。
これほど華やかで派手に彩られたイベントは横浜市では最大規模といってよい。
この “はまっパレ!” のスタート地点は山下埠頭で、ゴールは伊勢佐木町となる。
全長3.8キロメートルの道のりをおよそ1時間半で通り抜ける。
コースの設計上そうなったとはいえ、市内有数のビッグイベントを締めくくる場所に
伊勢佐木町をもってきたのも、歴史あるこの地に敬意を表した証しともいえよう。
とはいえ歴史があるというだけで、いつまでもヨコハマの中心でいられるわけでない。
現に市内でもっとも人が集まる場所は横浜駅西口だったり、みなとみらい だったりと
他のスポットにとって代わられている。
もはや伊勢佐木町がヨコハマ最大、いやっ京浜エリア屈指の繁華街だったのは
過去のことだ。
中心市街地というのは固定されたものではなく、
さまざまな要因によって立地変動を余儀なくされるものである。
そうはいっても、生物と同じように都市にも “遺伝子” がしっかりと根づいていて
容易に組み換えることはできない。
立地条件がよい場所は時間の経過とともに、
より経済活動がしやすいところへと移動していくが、
その場所に根ざした遺伝子は何年たってもそう簡単に変化することはない。
では、古くから伊勢佐木町に深く根を下ろした遺伝子とは――それは
「賑わい」 という因子ではないだろうか。
この街はその昔、いつも “賑わって” いた。
毎日がお祭りのような雰囲気を醸し出していた。
街のいたるところに芝居小屋が林立し、その代表的なものとしては 「賑座」 があり、
それは現在の伊勢佐木町三丁目にあたる 「賑町」 にあった。
このような歴史をひもといてもわかるように、明治・大正の時代からこの街には
“賑わう” ことが確固たる遺伝子として深く太く根づいているのだ。
以前のように賑わいを少しでも復活させることで、
往年の活気を少しでも取りもどせるのではないだろうか。
それはなにもこの街特有のものではない。
全国津々浦々に、
規模の大小こそあるが同様の事情を抱えた街がいくつもあるはずである。
<以下、つづく>

Posted by やすちん at
00:36
│Comments(0)
2015年11月23日
横浜・伊勢佐木町 物語<84>
イセザキモールに歓喜の渦が巻き起こる
その瞬間、普段はさほど賑わいをみせないこの街が異様な熱気に包まれた。
きょうのパレードに合わせて派手に彩られた大きなフロートが街の入り口にある
ウェルカムゲートをくぐり抜けると、その高揚感はさらに激しさを増してきた。
これまでにも登場してきた 「フロート」 とはパレードなどに使用される特殊なクルマで、
わが国では東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオ・ジャパンでお馴染だ。
車輪部分をできるかぎり覆い、
地面から浮いているかのように見えるためフロートと呼んでいる。
側面に 「イセザキモール1~7st.&横浜マツザカヤ」 と記されたこの大きなフロートが
やがて横浜松坂屋の前にさしかかると、ゆったりとした速度をより一層ゆるめて
ほとんど停止状態となった。
それが合図であるかのように、フロート上に陣取る3人の若者からなるミュージシャン
JOHNLOSが手際よく演奏をはじめた。
もちろん、その曲は 「伊勢佐木町ブルース」 ――。
その昔、いまは亡き青江三奈が歌って大ヒットした曲を今風にロック調で巧みな
アレンジをほどこし、軽快なリズムに乗せて奏でている。
山下埠頭を出発したときからすでに何回か繰り返し演奏してきているのだが、
フロートが伊勢佐木町に入ってきたときから彼らの演奏は一層熱を帯びている。
リーダー海野哲也のアレンジは原曲の良さを損なわず、そこに爽やかさが加味されて
独特の清涼感を醸し出している。衰退が叫ばれて久しいこの街を活気づけるには、
まさにうってつけのサウンドといってよい。
この 「伊勢佐木町ブルース」 が大ヒットを飛ばしたのは、このパレードが行われている
平成19 (2007) 年の40年ほど前になる昭和43 (1968年) のことだった。
かつて、ここは東京・銀座と並び称される一大繁華街だったが、
この歌がリリースされたころはすでに 「伊勢佐木町」 の名前は徐々に大衆から
忘れ去られようとしているときだった。
ところが 「伊勢佐木町ブルース」 は予想をはるかに超えるミリオンセラーとなるなかで、
この街はふたたび脚光を浴び、その名を全国へと轟かせることになったのだ。
やがて、JOHNLOSと若さ溢れるチアガールたちを乗せたフロートが
伊勢佐木町の三丁目へと進んでいった。
いつもなら、二丁目と三丁目の境となる広い道路が来街者の回遊をさえぎり、
ここ三丁目からは徐々に人通りが少なくなっていく。
そして最西端となる七丁目ともなると人影もまばらで、もはやかつての面影はまったく
ないのだが、この日に限っては三丁目から四丁目あたりは沿道を埋め尽くす群衆の
列が途絶えることはない。
「昔は毎日がこのような賑わいだった……」
晴れやかなパレードをつぶさに眺めていた伊奈正明はこうつぶやいた。
伊奈は平成15 (2003) 年に店舗を畳むまで、
この街で長い年月にわたってレコード店 「ヨコチク」 を経営していた。
現在は、以前に店のあった三丁目の通りから一歩裏手に入ったビルの地下に
オフィスを構え、すでに80代の半ばにさしかかろうという高齢にもかかわらず、
このときはまだ現役で音楽関係の仕事に携わっていた。
この街にとって救世主となった 「伊勢佐木町ブルース」 が発売されたのは、
伊奈が働き盛りの40代半ばのときだった。
だが、当初はさほど話題になることもなかった。
それでも、伊奈をはじめ街全体がひとつになってプロモーション活動に尽力した。
この曲をイセザキ再生の起爆剤にしよう、かつての勢いを再現させよう――。
そんな強い想いが天に届いたのか、やがてヒット街道を驀進することになったのだ。
その輪の中心にいた伊奈は、この楽曲をミリオンセラー商品に仕立て上げた
“大ヒットづくりの仕掛け人” なのである。
<以下、つづく>

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at
01:32
│Comments(0)
2015年11月22日
横浜・伊勢佐木町 物語<83>
最先端の 「みなとみらい」 と伝統の薫る 「馬車道」
赤レンガ倉庫の背後には高さ296メートルを誇る
当時としては日本一の超高層ビル 「ランドマークタワー」 が視界に入る。
ここから先は 「みなとみらい21」 と呼ばれ、
いまや中華街と並ぶヨコハマの集客スポットとなっている。
休日ともなると多くの来街者で溢れかえり、身動きもできないほどだ。
その数は年間4千万人といわれる。
“はまっパレ!” のコースからは外れるが国際橋のほうに繰り出すと、
そこにはいくつもの高層ビルが林立し、青い空をつく近代的な景観をつくっている。
だが人工的に建設された都市という印象はぬぐえず、歴史を刻んだ重厚感あふれる
オシャレが正統だとされるヨコハマのイメージとはかなり遠い感じがする。
なので、開港後いち早く発展してきた伊勢佐木町と比べると
人出こそはるかに上回るが、こと歴史の深さは比べようもない。
さて、パレードの中間地点となる赤レンガパークを後にした隊列は
「横浜ワールドポーターズ」 のところで左折し、万国橋を渡ってさらに直進する。
横浜第二合同庁舎を右手にみて進むと、
そこからは一転して歴史を感じさせる 「馬車道」 だ。
開港以降ヨコハマの街は急速に整備されていき、
この通りの商店主たちも競って街路樹や松を植えるなどして道路を整えた。
これが日本での近代的街路樹のはしりとされ、
馬車道には 「近代的街路樹 発祥の地」 の記念碑がつくられている。
また明治5 (1872) 年には日本初のガス灯が設置された。
この記念碑も関内ホール前におかれている。
関内地区はヨコハマに外国人居留地がつくられて以来、
多くの外国人を受け入れてきたエリアだ。
この道は関内地区とつなぐだけではなく、
伊勢佐木町を中心とする関外地区と横浜港を結ぶメインストリートだった。
当時の外国人はこの通りを馬車で往来、そこから 「馬車道」 という名前がついた。
さまざまな国籍の人が行き来したことからか、
馬車道エリアには現在も世界各国の料理店が存在する。
スペイン、インド、トルコ、メキシコ、フィリピン、ギリシャ……等々、
実にさまざまな国々のレストランを発見することができる。
馬車道でまず目を引かれるのが 「神奈川県立歴史博物館」 だ。
八角型のドームをもつネオバロック式の建物が圧倒的な存在感を誇る。
この建物は明治37 (1904) 年、
横浜正金銀行 (のちの東京銀行) 本店として竣工された。
関東大震災によってドーム部分が消失したが、その後復元された。
半円型の入口と三本円柱で支えられた白いバルコニーが印象的な
「BankART1929」 は、横浜市が推進する歴史的建造物や港湾施設等を活用した
文化芸術創造の実験プログラムとしてつくられたギャラリーだ。
bankART=バンカートとは、旧第一銀行と旧富士銀行、
このふたつの建物を芸術文化に利用するという意味の造語で、
ふたつとも昭和5 (1929) 年に建てられた。
世界恐慌がはじまったこの年はニューヨーク近代美術館 (MOMA) が設立された
年でもあり、芸術関係者にとっては記念すべき年だった。
同じように歴史建造物が多く残る日本大通りやみなと大通りよりも、
もっと悠然とした雰囲気を醸し出す馬車道――そんなレトロなエリアであっても、
伝統を尊重しながら新たな文化・芸術を発信しようという動きは着実に進んでいる。
そういった歴史の刻まれた沿道を左右に見ながらJOHNLOSの3人を乗せた
フロートは馬車道を通りぬけ、やがて 「伊勢佐木町」 へと入っていく――。
<以下、つづく>

Yahoo!「馬車道の画像」より
Posted by やすちん at
23:38
│Comments(0)
2015年11月21日
横浜・伊勢佐木町 物語<82>
かつて貿易の要として活躍した 「赤レンガ倉庫」
12番目となる伊勢佐木町チームが「赤レンガパーク」に足を踏み入れると、
到着を待ちかねていた観客たちは大歓声と拍手でフロートを迎えた。
この年、同チームは客船をイメージさせたフロートで参戦した。
ここから見える大桟橋にも、
大きさこそまるで違うがちょうど似たような船が停泊しており、
それと比べてみても、できのよい “模造船” であることがわかる。
赤レンガパークは “はまっパレ!” の審査会場でもあり、
“船上” に陣取るJOHNLOSもここぞとばかりに、
アレンジされた 「伊勢佐木町ブルース」 の現代版を熱唱した。
ちなみに、翌年の平成20 (2008) 年はこの年と同様、
やはり彼らの演じた伊勢佐木町チームが準 “はまっパレ!” 大賞を獲得している。
赤レンガパークに隣接して建つ 「横浜赤レンガ倉庫」 は明治44 (1911) 年5月、
明治政府により新港埠頭整備の一環で、国の模範倉庫として建設されたのが
その始まりだ。
開港以降、
日を追うごとに規模を増やしていく貿易の要として赤レンガ倉庫は活躍した。
開港直後は羊毛や葉タバコ、洋酒などの貨物が多く倉庫に保管されていた。
また第二次大戦直後には米軍に接収され開港司令部となる。
その後、接収が解除され、ふたたび貿易に使用されるも次第に取扱貨物量が減り、
平成元 (1989) 年には倉庫としての役目を終える。
そして平成14 (2002) 年、ヨコハマの新しい観光施設として
現在の赤レンガ倉庫がオープンした。
当ブログのタイトルバックに使われているのがオープン直後の夜景だ。
それと同時に周囲も赤レンガパークとして整備された。
<以下、つづく>

Yahoo!「赤レンガ倉庫の画像」より
Posted by やすちん at
23:59
│Comments(0)
2015年11月20日
横浜・伊勢佐木町 物語<81>
横浜港の歴史は 「象の鼻」 からスタートした
時計の針はそろそろ正午を指そうかというころ、
伊勢佐木町チームのフロートは山下公園西端と横浜税関、赤レンガパークを結ぶ
「山下臨港線プロムナード」 にさしかかった。
500メートルほどの遊歩道であり、
桜木町駅から港の見える丘に通じる 「開港の道」 の一部と位置づけられている。
すでに日はすっかり高くなり、
ますます明るさを増した太陽が横浜湾をキラキラと照らしている。
視界は一気に開け、情緒的な歴史建造物のセピア色に変わって、空と海の鮮やかな
ブルーが目に飛び込み、フロート上に陣取るJOHNLOSの3人は思わず唸った。
「わずかな距離を移動するだけで、こんなに景色が変わるのか……」
幼いころからヨコハマを熟知しているつもりでいたリーダーの海野哲也でさえ、
さまざまな顔をもつ街の多様性に驚きを隠せなかった。
山下臨港線プロムナードから海を眺めると、
大桟橋のつけ根から左手へ伸びる防波堤が望める。
この防波堤を上空から見ると象の鼻に似ていることから、
そのまま 「象の鼻」 という愛称がついた。
なので、この防波堤のある一帯は 「象の鼻地区」 と呼ばれている。
海岸線を見てもわかるように、このへんは横に長い浜辺が延々とつづく。
それで 「横浜」 という地名が誕生したくらいだ。
横浜港の歴史はこの象の鼻地区からスタートした。
現在、象の鼻にある防波堤の先には大桟橋の鉄橋が長く伸びているが、
開港当時は防波堤も橋もなく、砂州の中央に2本の突起状がある波止場だった。
後に “イギリス波止場” と呼ばれるこの地域から、
関内地区は外国人居留地と日本人居留地に分けられた。
元治元 (1864) 年には居留地側、ちょうどホテルニューグランドの前あたりに
東波止場 (後のフランス波止場) が築かれたが、
大正期の関東大震災で消失してしまった。
山下臨港線プロムナードの向かいには
「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」 が見える。
ここは明治27 (1894) 年の完成時には 「大さん橋埠頭」 と呼ばれ、
横浜港の玄関として活躍してきた。
現在の大桟橋は平成14 (2002) 年にリニューアルしたものだ。
ターミナルには、外国船では 「クイーンエリザベス2号」 、日本船では 「飛鳥Ⅱ」 など、
3万トンを超える豪華客船が停泊することもある。
<以下、つづく>

Yahoo!「象の鼻の画像」より
Posted by やすちん at
00:55
│Comments(0)
2015年11月19日
横浜・伊勢佐木町 物語<80>
キング、クイーン、ジャック――横浜三塔
異国情緒あふれる建物がひしめく 「日本大通り」 と一本北側にある
「みなと大通り」 にあって、市民をはじめ多くの人々に “伝説化” されているのが、
それぞれキング、クイーン、ジャックの愛称をもつ 「横浜三塔」 である。
神奈川県庁本庁舎の、横に長く左右対称の建物の中心に伸びる高さ48.6メートルの
塔がいわゆる 「キング」 だ。
石とスクラッチタイルを貼りこみ、西洋建築に日本様式を取り込んだ地上5階、
地下一階の庁舎は帝冠様式の先駆けとなった建築物だといわれている。
いまなお現役となる県庁の本庁舎で、国登録有形文化財に指定されている。
そのキングの塔の斜め向かいの位置にあり、日本大通りの駅を挟んだみなと大通りに
あるのが横浜市開港記念会館だ。
ネオルネッサンス様式の赤レンガ造りの建物は美しくロマンティックである。
通りの角部分にそびえる時計塔が開館のシンボルで、「ジャック」 の愛称で
広く親しまれている人気スポットである。
そして、みなと大通りから山下臨海線プロムナードに向かう地点にあるのが
横浜税関であり 「クイーン」 の塔をもつ。
目の前はもう横浜湾となる。
現在の税関庁舎は三代目で、この三代目庁舎は昭和9 (1934) 年に竣工された。
西洋建築様式の建物の上に、イスラム教寺院のような淡いブルーグリーンのドームを
乗せた塔が立っている。
この横浜三塔には、キング・クイーン・ジャックが地上から同時に見える場所すべてを
巡ると願いが叶うという伝説がある。
その場所は市内に三カ所あり、伝説の由来はふたつある。
ひとつは三塔が震災など多くの試練を経て今に残っていることから、
困難を乗り越え願いが叶うというもの、もうひとつは外国人の船乗りたちが
航海の安全を願掛けしたというものだ。
ちなみに、神奈川県本庁舎の正面入口前、大桟橋の屋上、
赤レンガ倉庫の岸壁の突端が、三塔すべてが見える場所である。
こうした歴史的建造物の多くが、
一度は関東大震災や戦争などで消失したり破損したりした。
ヨコハマは震災や戦争の被害が大きい地域だ。
しかし、度重なる被害にも屈せず、
ヨコハマに関わる人々はこうした歴史的建造物を何度となく復活させてきた。
それはもっとも歴史ある街の伊勢佐木町でも同様だ。
代々、横浜市に住む人々は街の発展の原動力となった異国文化を尊重し
愛してきたのだろう。
<以下、つづく>

Yahoo!「横浜三塔の画像」より
Posted by やすちん at
23:07
│Comments(0)
2015年11月18日
横浜・伊勢佐木町 物語<79>
異国文化を色濃く映すストリート 「日本大通り」
シルクセンターを抜けると左手に 「日本大通り」 がある。
パリのシャンゼリゼを模してつくられたという粋な通りには神奈川県庁をはじめ、
横浜開港資料館、横浜港郵便局、横浜地方・簡易裁判所、日本銀行横浜支店など
横浜市の重要な施設が立ち並ぶ。
西洋式のエキゾチックな建造物も多く見られ、爽やかな海沿いの通りとはまた違った
総延長およそ430メートルのムードあるワイドなストリートだ。
この日本大通りは、日本初の西洋式街路としてイギリス人の技師R・H・ブラントンの
設計により明治3 (1870) 年にほぼ完成した。
通車道幅12メートル、植樹帯、歩道幅12メートルと広い幅員がとられたこの通りは、
明治時代には人力車やまだ数少ない自動車が往来する街のメインストリートとなる。
秋に見事な黄金の葉をつけるイチョウ並木は関東大震災後に植えられたものだ。
関内駅に向かう日本大通りの突き当たりには 「横浜公園」 がある。
ここに横浜市音楽堂や野球場などが建設され、
公園全体が整備されたのが昭和4 (1929) 年だ。
その5年後にはベーブルース、ゲーリックをはじめとする大リーガー選抜チームが
訪れて全日本チームと対戦した。
すでに音楽堂はなくなってしまったが、野球場はゲーリック球場、平和球場、
横浜スタジアムと名前を変え現在も残っている。
山下通り側から日本大通りに入ってすぐ左手に、
横浜の歴史を今に伝える 「横浜開港資料館」 がある。
旧館と新館からなり、昭和初頭の昭和6 (1931) 年に建てられた旧館は
当初イギリスの総領事館だった。
旧館が建つ以前の明治2 (1869) 年にはレンガ造りのイギリス領事館がこの地に
建っていたが、関東大震災で倒壊している。
その後復興し、新館も増設され、
昭和56 (1981) 年に横浜開港資料館としてオープンした。
<以下、つづく>

Yahoo!「日本大通の画像」より
Posted by やすちん at
00:04
│Comments(0)
2015年11月17日
横浜・伊勢佐木町 物語<78>
フロート上から眺める古くて新しいヨコハマの街
伊勢佐木町チームのフロート上から “ニュー伊勢佐木町ブルース” をはじめ3曲を
繰りかえし演奏するJOHNLOSは、歌いながらもヨコハマの街をウォッチングしていた。
地上からおよそ3メートルというけっこう高い位置から街の様子を見下ろせる。
俯瞰しながらも建物や自然の景観など具体的な形もしっかりと確認でき、
絶妙のバランスでヨコハマの街をとらえることができるのだ。
「ヨコハマってこんなところだったかな……」
グループのリーダーである海野哲也は、
担当するアコースティックギターを抱えて演奏している合間にそんな感慨にふけった。
母親が横浜市の出身で伊勢佐木町の野澤屋 (のちの松坂屋、2008年に営業終了)
に勤めていたこともあり、幼いころからヨコハマにはよく遊びにきていた。
だが、いまフロートの上から眺めているヨコハマはなんだか違う街のごとく新鮮に映る。
それはまた、リードボーカルの桜木れおやリードギターの寺本憲之も
同じ感覚を抱いていた。
れおは大阪、憲之は熊本の出身で、哲也ほどではないが
上京後には何度かヨコハマを訪れている。
でも、3メートルもの高さからゆっくりと移動しながらヨコハマを眺めたのは
きょうが初めてだ。
雲ひとつない好天のもと百万人に迫ろうかという大観衆のなかを、
フロート上から見下ろすヨコハマの風景は実に爽快だった。
“はまっパレ!” は、はからずも彼らにとってこの街を見つめなおし、
新たな発見をする小さな旅となっていく。
視線の先に 「シルクセンター」 が見えてきた。
正式名称は財団法人シルクセンター国際貿易観光会館であり、
横浜開港100年の記念事業として昭和33 (1958) 年にオープンした。
神奈川県や横浜市、関係業界が協力し、生糸・絹産業および貿易の振興、
観光事業の発展のため、シルク博物館や横浜生糸取引所などが入居している。
ヨコハマが開港したころ、わが国の輸出品のトップは生糸だった。
特にアメリカ向けの輸出生糸は、最盛期であった明治後期から昭和初期にかけては
世界生産量のおよそ60パーセントを日本が占めていたという。
絹いわゆるシルクは開港以後、
日本が世界とつながり発展していくための大きな役割を果たしていたのである。
<以下、つづく>

Yahoo!「シルクセンターの画像」より
Posted by やすちん at
23:45
│Comments(0)
2015年11月16日
横浜・伊勢佐木町 物語<77>
この数年 “はまっパレ!” は 「開港への道」 がテーマに
スーパーパレードはゆっくりと山下公園通りを進んでいく。
両側の沿道には年に一度の大パレードを楽しもうという聴衆で埋め尽くされていた。
隊列の3番目は主催者でもある「横浜商工会議所・神奈川県・横浜市」だ。
フロートで参加しているチームのなかでは一番手であることもあって
歓声はひときわ大きくなった。
フロートの先頭には神奈川県知事の松沢成文と横浜市長の中田宏が仲よく並び、
イベントのホスト役として笑顔で多くの声援にこたえていた。
この “はまっパレ!” は毎年テーマを設けている。
2年後に迎える横浜開港150周年に向けて、平成17 (2005) 年からの5年間は
「開港への道」 を共通テーマに掲げることになった。
それに加え、一年ごとに文化テーマを設けてその年の特色を出している。
この年の文化テーマは 「開港への道~横浜ファッションロード~」――ハマトラが
大流行した1970年代後半から80年代にスポットを当てたものだ。
次いで、横浜市をフランチャイズとするプロ野球チーム 「横浜ベイスターズ&TBS」
のフロートに乗ったチアリーディングの一団が躍動感いっぱいに演じ、さらには
シウマイ弁当を模した 「崎陽軒」 のユーモアあふれるフロートが観客の笑いを誘う。
それぞれが個性を競うフロートは “はまっパレ!” に欠かせない魅力を演出する。
この年は全48チーム中、9チームがフロートで参加し、
パレートの12番目にエントリーされている伊勢佐木町チーム
「イセザキモール1~7st.&横浜マツザカヤ」 もそのひとつだ。
今回はそのフロート上に若手ロックバンドJOHNLOSの姿があった。
東京・錦糸町などで路上ライブを中心に活動を続けていた彼らと伊勢佐木町を
結びつけたのは、往年の名曲 「伊勢佐木町ブルース」 だった。
かつて青江三奈が歌い一世を風靡したこの曲をロック調にアレンジし持ち歌に
したことが縁となり、定期的に伊勢佐木町で路上ライブをするようになった。
その後は、のちに閉店されることになる横浜松坂屋の屋上にステージを移し、
街の活性化をめざすべく活動を続けている。
このとき、メンバーの3人はいずれも20代後半で、明るく染めた髪にラフな服装の、
いわゆるイマドキの青年たちだ。
とはいえ、最近の若者にしては礼儀正しく初々しささえ感じさせる。
40年ほど前に大ヒットした 「伊勢佐木町ブルース」 は、
そんな若い彼らの手によって現代風に甦り、
こうしてフロートの上から百万人近くの大観衆に新鮮な歌声が届けられた。
https://www.youtube.com/watch?v=k52-eR0Q6DA ←クリック~!
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
01:52
│Comments(0)
2015年11月15日
横浜・伊勢佐木町 物語<76>
市民と観光客に安らぎのひとときを与える 「山下公園」
第55回 “はまっパレ!” スーパーパレードの出発地点より進行方向右手には
「山下公園」 が広がっている。
この公園は昭和5 (1930) 年に関東大震災の復興事業として、
波打ち際に廃棄されていた焼土やレンガなど被災した建物の瓦礫を埋め立てて
開園した日本初の臨海都市公園である。
公園建設の際には、市民の多くが荷車を引き工事に参加をしたという。
山下公園のシンボルとなる氷川丸は
昭和5 (1930) 年に日本郵船が三菱横浜造船に竣工させた重さ1万2000トン、
全長163.3メートルの貸客船である。
この氷川丸は昭和35 (1960) 年8月に引退、
翌年6月に山下公園地先に係留され一般公開されるようになった。
平成18 (2006) 年には赤字のため閉鎖されたが、
平成20 (2008) 年4月より 「日本郵船氷川丸」 としてリニューアルオープン、
氷川丸の歴史を展示するコーナーやアールデコ調に復元された船内などが
一般公開されている。
山下埠頭を出てすぐ左、山下公園と向かい合う場所には
横浜マリンタワーがそびえ立つ。
およそ50年前の昭和36 (1961) 年1月に
横浜開港100周年記念事業としてオープンした。
横浜港を象徴する塔であり、一般公募によって 「マリンタワー」 の名がつけられた。
高さは106メートル、世界最高の灯台としてギネスブックにも掲載されている。
そして横浜開港150周年となる平成21 (2009) 年5月にはリニューアル工事も
終わり、すっかり装いも一新された雄姿を見せている。
かつて横浜市民らが瓦礫の山のなかリヤカーをひいて山下公園の開園に尽力した
ように、氷川丸もマリンタワーも時代変化の波により閉鎖の憂き目をみたが、
ふたたび現代を生きる人々によって再建された。
山下公園は、
今も昔もヨコハマの復興と再生を象徴するような独特の雰囲気を秘めている。
<以下、つづく>

Yahoo!「山下公園の画像」より
Posted by やすちん at
01:17
│Comments(0)
2015年11月14日
横浜・伊勢佐木町 物語<75>
高台から街を見下ろす 「山手地区」 と 「港の見える丘」
その元町商店街より少し山側に位置する代官坂を上ると、
眼の前には 「山手外国人墓地」 が視界に入ってくる。
開港の年となる安政6 (1859) 年、開国に反対する攘夷派の暴徒に殺害された
ロシア艦隊の隊員2人が元町の増徳院に埋葬された。
この増徳院は文久元 (1861) 年に境内の一部と隣接する土地を
外国人の埋葬地として貸与し、これが山手外国人墓地の礎となった。
敷地内にはアメリカ、イギリス、ロシア、オランダなど各国の記念碑が建てられており、
多様な国籍の人々がヨコハマに暮らしていたことを物語る。
さらにその先には高級住宅街の 「山手地区」 が広がる。
長く外国人居留地であったこのエリアには、
豊かな緑のなかに瀟洒な洋館が当時の面影のまま残っている。
この山手地区につながる 「港の見える丘」 は、
その名が示すとおり横浜港を見下ろす高台に位置する。
幕末から明治初期にかけてイギリス軍、フランス軍の駐屯地であった。
そしてヨコハマが開港し外国人が多く暮らすようになると、
街の活性化と同時に日本人との間のトラブルも増えた。
そのような状況下で、自国民を守るという名目で軍隊が日本に駐留することになった。
戦後アメリカに接収されたが、それが解除されると日本が公園用地として取得し、
昭和37 (1962) 年に港の見える丘公園としてオープンした。
この展望台に立つと、まずは横浜ベイブリッジが目に飛び込んでくる。
さらに周りを見渡すと、ヨコハマの都心臨海部が一望できる。
山下公園、大桟橋、みなとみらいの観覧車……等々、
ちょっと眺めただけでも馴染みのあるスポットを見つけることができる。
さて、先ほどスタート地点の山下埠頭を出発した 「ザよこはまパレード」
いわゆる俗称 “はまっパレ!” の隊列は、これらの名所に思いをよせつつ、
中間地点の赤レンガパークをめざしていった。
<以下、つづく>

Yahoo!「港の見える丘の画像」より
Posted by やすちん at
00:34
│Comments(0)
2015年11月13日
横浜・伊勢佐木町 物語<74>
開港とともに西洋文化の影響を受けた 「元町」
中華街の目と鼻の先にありながら、元町から山手地区は中華街とはまったく異なる
雰囲気を漂わせるクラシックな西洋情緒あふれるエリアである。
高級住宅街となる山手地区から坂を下った場所にある「元町」は、明治・大正期から
続く老舗の洋品店や服飾店、洋菓子店などがいまも残るファッションストリートだ。
メインストリートである元町通りは全長600メートル、ここに約450軒の店が集積する。
開港後、横浜村 (現在の横浜市) は日本大通りを境に
日本人商業地区と外国人居留地区とを分ける事業計画を発表し、
万延元 (1860) 年には横浜村に住む90戸を隣接する本村に強制的に移転させ、
地名を 「本村」 から 「横浜元町」 に変更した。
当時、元町の住民は大半が農業や漁業を営んでいた。
だが、山手の外国人居住地の人口が徐々に増えていき、
元町通りは居住地である山手と仕事場である関内を結ぶ、
外国人たちが日常的に利用するストリートとなる。
すると次第に外国人向けに商売をはじめる人が増えていった。
これが現在の元町の原型である。
1970年代の終盤から1980年代の初頭にかけて元町は
「ファッションの街」 として一躍注目を浴びた。
当時、横浜・元町を中心に流行していたファッションを 「ヨコハマ・トラディショナル」
と呼び、それを女性誌がこぞって取り上げたことから一気にブレイク、
全国に “ハマトラ” ブームが広がった。
元町の老舗の多くは、
このように開港で流れ込んできた西洋文化の影響を受けて誕生している。
長く外国人居留地であった山手地区に西洋文化が浸透し、
やがてそれは元町の文化となり定着していった。
そしてまた、同じ歴史あるヨコハマの商店街でありながらも、時代とともに活力を
なくしていった伊勢佐木町とは異なり永続的な発展を遂げている。
<以下、つづく>

Yahoo!「横浜元町の画像」より
Posted by やすちん at
23:57
│Comments(0)
2015年11月12日
横浜・伊勢佐木町 物語<73>
歴史あるヨコハマを象徴する日本最大の 「中華街」
パレードの出発地点となる山下埠頭の近くには、
みなとみらい地区と並んでヨコハマを代表する集客スポット 「中華街」 がある。
およそ0.2平方キロメートルの中に500を超える店が軒を連ねる
わが国最大の中華街だ。
日本にはヨコハマ以外にも神戸・南京町や長崎・新地に中華街があって、
これらが三大中華街と呼ばれる。
このなかではヨコハマの中華街がもっとも規模が大きく突出している。
150年前に横浜港が開かれると、
ヨコハマには商人を中心に世界各国から多くの人々が訪れるようになった。
その流れを受けて現在の山下町や山手町の一帯は外国人居留地として開発されて
いくことになる。
広東や上海などを中心に中国からもたくさんの来訪者があった。
彼らの多くは祖国にある西洋商館で働いていた経験をもち、西洋の言葉に通じていた。
さらに日本人とは漢字を通して筆談で意志の疎通ができたため、
言葉のわからない西洋人と日本人の間に入って貿易を仲介していたという。
また、日本の海産物を中国へ輸出し台湾から砂糖を輸入するなど直接の貿易も盛んに
行われていた。
彼らは港町ヨコハマの発展にとって、きわめて重要な存在であった。
慶応から明治への過渡期であった明治元 (1868) 年、このようなヨコハマに渡ってきた
中国人、いわゆる華僑も外国人居留地として整備がすすむ山下町の一角に居住する
ようになる。
居住地区には関帝廟や中華会館、中華学校などが続々と建設されていき、
これが中華街の原型となっていった。
ここ中華街はいつも多くの人出で賑わっており、
もはやすっかり勢いをなくした伊勢佐木町とは対照的だ。
雑多でエネルギッシュな魅力を放つ中華街は開港以来、多くの文化を受け入れ
日本人と共存し、震災や戦争など度重なる困難を乗り越え発展してきたヨコハマを、
ある意味で象徴する場所ともいえる。
<以下、つづく>

Yahoo!「横浜中華街の画像」より
Posted by やすちん at
00:15
│Comments(0)
2015年11月11日
横浜・伊勢佐木町 物語<72>
市内のいたるところに観光スポットがひしめき合う
パレードの先陣を切るのは、横浜市にある小学校の鼓笛隊や
地域のバトンクラブなどの子どもたちが可愛らしく行進する 「キッズパレード」 だ。
それに続き、ヨコハマゆかりの企業や団体が参加し、おのおの趣向を凝らした
出し物を提供する 「スーパーパレード」 が都心臨海部を闊歩する。
パレードの審査が行われる赤レンガパークでは 「スーパーエキシビジョン」 として、
梯子乗りや阿波踊りなどの日本伝統の演舞から、サルサダンスやバリ舞踏と
いった国際色豊かな演目まで、さまざまなパフォーマンスが繰り広げられる。
パフォーマーたちの熟練した演技に、会場には何度も大歓声と拍手が沸き起こった。
メインパレードとなる 「スーパーパレード」 には毎年50前後のチームが参加している。
第55回目となるこの年には48チームがエントリーしていた。
参加チームにはヨコハマを代表する企業や団体が多い。
こうした歴史のある企業や団体の有志たちが一堂に会するイベントは実に壮観だ。
全チームのほぼ6分の1は華やかな装飾をほどこした 「フロート」 に乗って登場した。
伊勢佐木町チームも数少ないフロート採用組のひとつだ。
以前は派手なフロートを従えて参戦したチームも多かったが、経費削減のムードが
大会全体に広がってきたのか、フロート組はめっきり少なくなってきた。
このイベントをみても、景気停滞の影響があらわれている。
だからだろうか、もはや希少となったフロートが登場すると、
観客がひしめく沿道はいっそうの盛り上がりをみせる。
スーパーパレードはスタート地点の山下埠頭を出発し、途中、審査会場が設置されて
いる赤レンガ倉庫を経由してゴール地点となる伊勢佐木町六丁目に到着する。
このパレードではどのチームが観客に強くアピールしていたか、
それを審査して表彰するのだ。
またパレードの通過地点や周辺には、だれもが知る有名なエリアが数多く並んでいる。
500軒以上の中華料理店がひしめく中華街や、老舗の有名洋品店が軒を連ねる
元町をはじめ、外国人居住地だったころの面影を残す山手地区や隣接する
港の見える丘、最先端のエンターテインメント施設が集まるみなとみらい地区、
歴史ある建造物が残る馬車道……等々、これらは一部にすぎない。
市内にはさまざまな由緒あるスポットがひしめき合う。
これだけ多くの観光名所を有する都市は全国でも類をみない。
ヨコハマの大きな特徴は、
伝統だけに寄りかからず時代の要求に合わせて変化を続けているところだ。
レトロとトレンドが巧みに共存するこの街は、
訪れる人にとって歴史に触れた感慨と新鮮な興奮を味あわせてくれる。
伝統的でありながら決して古びない。
それが多くの人々を惹きつける 「観光都市ヨコハマ」 の所以たるところだろう。
午前10時30分、オープニングセレモニーがはじまった。
ガヤガヤと一種雑然とした賑わいが広がっていた会場の空気がピリッと引き締まる。
10時45分、横浜市立下野庭小学校のマーチングバンドを先頭に元気よく
キッズパレードがスタートすると、山下埠頭はふたたび大歓声と熱気に包まれた。
そして11時15分、いよいよメインとなるスーパーパレードの出発時間がやってきた。
露払い的な役目もすっかり恒例となった「神奈川県警察音楽隊」の高らかな演奏が
出発の合図となり、48組の隊列がゆっくりと出陣の準備をはじめた。
いよいよ “はまっパレ!” の開幕である。
<以下、つづく>

Yahoo!「“はまっパレ!”の画像」より
Posted by やすちん at
00:42
│Comments(0)
2015年11月10日
横浜・伊勢佐木町 物語<71>
全国でも類をみない観光都市ヨコハマ
平成19 (2007) 年5月3日は文字どおり 「五月晴れ」 と呼ぶにふさわしい快晴だった。
抜けるような青空と新緑に反射する陽の光がヨコハマの街を鮮やかに照らし出す。
パレードを祝福するかのような好天のもと、パレードの参加者も、
これを見ようと朝早くから沿道を埋め尽くした見学者も、
期待と緊張の入り混じった独特の高揚した空気に包まれていた。
この “はまっパレ!” は、ヨコハマが開港した150年前の安政6 (1859) 年以来、
横浜市の名物イベントとして毎年開催される “みなと祭” に昭和29 (1954) 年から
取り入れられた。
第1回目は開港記念日である6月2日に開催された。
以降、しばらくは5月の土曜日や日曜日に行われるなど開催日は定まらなかったが、
第17回イベントの昭和45 (1970) 年からは毎年5月3日に開催するのが慣例となる。
横浜開港記念みなと祭は第二次世界大戦後から数年を経て、
ヨコハマの街が少しずつ落ち着きを取りもどしはじめたころ、
「街の発展と希望の象徴となる、横浜らしいお祭を~」 というコンセプトのもとに誕生した。
「世界とつながる港町」――。
そんな特色を発揮できるイベントとして 「ザよこはまパレード」、いわゆる “はまっパレ!”
と俗称される国際仮装行列が開催されることになったのである。
日本人も在留外国人も参加し、それぞれ特色のある仮装や一芸を披露しながら
陽気に横浜市内を巡るこのパレードは日本の都市型イベントの先駆けとなり、
全国のほかの地域にも大きな影響を与えてきた。
いまや横浜市周辺はもちろんのこと、遠方からも見物客を集めるこの催しは、
ヨコハマの街に欠かすことのできない年中行事の一大イベントとなったのである。
街に潤いを与え、なおかつ街を活性化していく手段としてよく 「イベント」 が行われる。
ここヨコハマでは平成21 (2009) 年、
開港150周年という記念すべき年を迎えることになった。
市内数カ所ではそれに関連した 「開国博Y150」 というテーマイベントが
4月28日から開催中だ。
そのオープニング直後には毎年恒例となる “はまっパレ!” が行われた。
そこで、当ブログの 『横浜・伊勢佐木町 物語』 を終えるに際して、
パレードのコースをナビゲートしながら伊勢佐木町を取り巻くヨコハマの主だった
名所を13回にわたって紹介していくことにする。
<以下、つづく>

Yahoo!「横浜市の画像」より
Posted by やすちん at
00:30
│Comments(0)
2015年11月09日
横浜・伊勢佐木町 物語<70>
この街はこれからも限りない可能性に向かっていく
平成21 (2009) 年2月15日、浅草公会堂では 「大江戸バンドセッション」 なる
音楽イベントが開催され、JOHNLOSも出演メンバーとして名を連ねていた。
このときに限らず、ストリート以外のライブハウスなどで演奏するときには何人かの
サポートメンバーが加わり、迫力あるステージを披露する。
この日も老舗の格調ある会場でのライブであり、
サポートメンバー数名が配備された重量感のあるコンサートとなった。
そんな晴れの舞台を最後に、寺本憲之がこのバンドから離れることになる。
また2年前の平成19 (2007) 年4月にはベースを弾いていた湯浅敏彦が
やはり脱退し、4人から3人になったことがあった。
このようにグループで活動しているミュージシャンというのは、
メンバーの脱退および加入など紆余曲折を繰りかえしつつ進化を遂げている。
マネジメントをする側も同様だ。
JOHNLOSも最近まで、
国民的歌手として著名な芹洋子の個人事務所に所属していたことがある。
だが、音楽スタイルやめざす方向性が少しずつ事務所サイドと乖離してきて、
およそ1年半後にはマネジメント契約を解消したという経緯がある。
今後はどういう軌跡をたどるのだろうか――
それは本人たちにも、まだわからないのかもしれない。
ただ、いえることは
ストリートミュージシャンとして街とともに成長、発展していくということだ。
それに、これまで街中や路上での活動が多かった彼らには
ファンの気持ちや願望がダイレクトに伝わってきた。
だからこそ、自分たちの欲求を満たすことよりも、
街に集まるファンの希望や願いを叶えてあげたいという思いが強い。
それを具体的な形にするならば、まずは 「紅白歌合戦」 に出ることだ。
ただ、決してそれが目標ではない。
いままで応援してきてくれた親兄弟やファン、そして自分たちを盛り上げてくれた
伊勢佐木町への恩返しとして形にあらわしたもののひとつが “紅白” への出場かな
と思っている。
なにやら 「ゆず」 が歩んできた道のりをそのまま踏襲するかのような話だが、
JOHNLOSとは曲調が異なるゆずを彼らは意識したことがない。
「自分たちは街ゆくファンをはじめ、場所を提供してくれる人たちの好意があるから
成り立っているということを常に念頭においている」
リードボーカルの桜木れおは、周りに感謝の意を込めてこう話す。
少し前まではメジャーデビューにこだわり、自分らの欲を求めていた彼らだったが、
最近はこの街に集うファンの希望を叶えていきたいというように考えが変化してきた。
好きなことをやるというのは多くの人々に迷惑がかかる。
それをあたたかい目で見守ってきてくれた街の人たちといっしょに夢を実現したい
――そんな思いが募る。
日本武道館や東京ドームでの公演、あるいは大阪出身のれおであれば大阪城ホール
などでのライブも夢見ているが、紅白歌合戦にこだわるのは親をはじめ年配のファン
や伊勢佐木町の人たちに感謝の気持ちをもっとも伝えやすい手段だと考えるからだ。
自分たちが売れたらそれで満足、たとえ伊勢佐木町のイベントに誘われても
メジャー然として袖を振るようなことは考えていない。
「売れてから地元の市民会館とかでライブをやるなんてこともあるだろうが、
そういった活動が伊勢佐木町でもできたらいいな~」
れおはそう言って一丁目から七丁目までの長い長いイセザキモールを見つめていた。
そして、みんなで触れあってなにかをつくるということを
大勢の人たちといっしょにしてみたい――それが彼らの究極の目標だ。
伊勢佐木町と自分たちはよく似ていると、れおはいう。
「もっと賑わっていきたい!」
「もっと成長していきたい!」
「もっと魅力的になりたい!」
それは過去の大繁栄とその後の衰退をまったく体験していないからこそ、
そんな前向きなプラス発想ができるのだ。
JOHNLOSも伊勢佐木町も限りのない可能性に向かって
これからもチャレンジしていくことだろう。
街も人も止まってしまったら、そこで終わってしまうのだから――。
<以下、つづく>

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at
23:42
│Comments(0)
2015年11月08日
横浜・伊勢佐木町 物語<69>
まちおこしは三位一体となって成立する
松坂屋が伊勢佐木町から撤退することになり、屋上ライブも終焉を余議なくされてから
半年後の平成21 (2009) 年3月、JOHNLOSはふたたびこの街に帰ってきた。
その場所は以前と同じ牛山ビルだ。
この街を活気づけるには “ニュー伊勢佐木町ブルース” を力強く歌う彼らが必要となる。
そしてまた最近プロモーションライブをする場所が少なく、
世の中にアピールする機会が減っていたことを懸念したファンがビルオーナーの
牛山裕子にかけあったこともあり、やがて伊勢佐木町三丁目でのライブが復活した。
インディーズバンドでありマネジャーがいないJOHNLOSにとって、
ライブ活動の場所探しやプロモーション展開は骨の折れる作業だ。
そんなとき、この牛山ビルでのケースと同じように、ライブができるようなスペースを
見つけてきては所有者に交渉するといった形で応援してきたファンも少なくない。
ここまで多くの人たちがサポートを買って出るというのも、
彼らが人間性に優れ親しまれている証といえるだろう。
以前の “牛山ビルライブ” では階段と踊り場を活用して特設ステージをつくり、
それを見上げるような格好で、聴衆が公道に溢れて通行の妨げになったことが
苦情の原因となった。
そのときの教訓を生かし、個人の敷地内であればかまわないという警察の言葉を
思い出しつつ、今回は2階のフリースペースを使用することになった。
あの街でふたたび “ニュー伊勢佐木町ブルース” が熱唱できる――メンバーたちの
胸が高鳴った。
いまや夫婦そろって熱烈なJOHNLOSファンの梅沢修二は
平成19 (2007) 年5月3日の “はまっパレ!” を赤レンガパークで見物していた。
そのとき、12番目に登場した彼らの奏でる爽やかな音楽に初めて遭遇した瞬間から
即 “応援団” と化していた。
パレードはさらに赤レンガパークから馬車道を抜け伊勢佐木町へと向かっていく。
梅沢夫妻は恥ずかしがる暇もなく、
伊勢佐木町までの“追っかけ”を躊躇せずに実行した。
ネット上で彼らを応援する梅沢夫妻のブログネームは 「団塊のお父さんお母さん」、
この名前でJOHNLOSのブログやファンのブログに温かいコメントを送る。
また、それまで滅多に外出をしなかった生活が一変した。
近くに住んでいながらも伊勢佐木町にはあまり出かけることもなかった。
ところがライブのある日は必ず伊勢佐木町へ出かけるようになった。
音楽が、元気のなくなった街に人を呼ぶようになったのだ。
「最近はライブのある日が楽しみになってきた。仕事にもハリが出るしね」
梅沢はそういってMP3プレーヤーのボリュームを全開にしておどけてみせた。
そしてまた、ライブがない日でも伊勢佐木町へ足を運ぶようになったのである。
平成18 (2006) 年11月にストリートライブが途絶えて以来、
2年4カ月ぶりにJOHNLOSが伊勢佐木町三丁目に帰ってきた。
彼らがこの街にあらわれた当初、街の人たちは名前すら知らなかったのだが、
いまでは街にもっとも馴染みのある音楽アーティストとなった。
この間、松坂屋の屋上ライブや伊勢佐木町で実施した各種イベントにも
参加していたので、いまではすっかり “街の顔” になりつつある。
伊勢佐木町は集客のためにさまざまなイベントに力を入れていることは
前述したとおりだが、彼らが三丁目で復活させた音楽ライブもまた、
集客という意味では立派な役割を果たしているのである。
伊勢佐木町は柏市に比べるとストリートライブのメッカとしてそれほど有名でもなければ、
「ストリートブレイカーズ」 のようにアーティストたちをバックアップする団体も設備もない。
とはいえ、そこには 「アーティストを育てたい」 「活動の場を与えたい」 という
伊勢佐木町の人々の思いと、「伊勢佐木町を盛り上げたい」というJOHNLOSの
思いが相互作用することで、双方はほどよい具合に“共生”している。
そして、JOHNLOSのライブへと駆けつける多くの人々がいる。
まちおこしは、街の人、盛り上げる人、
そこに集う人――これらが三位一体となって成り立つのである。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
01:07
│Comments(0)
2015年11月07日
横浜・伊勢佐木町 物語<68>
ネットを彩る 『JOHNLOSコレクション』 とは
商店街同様、その周辺に住んでいる人々もJOHNLOSには熱い視線を送る。
伊勢佐木町の五丁目と六丁目の境となる通りを南下すると、
下町の雰囲気が色濃く漂い、いつも賑わいをみせている横浜橋通商店街に出る。
この活気ある町並みを通り抜けてしばらく歩くと
横浜市南区八幡町という人情あふれる住宅地に到達する。
そこに住む梅沢修二も彼らのことにはたえず気にかけているひとりだ。
会社への行き帰りと昼休みには毎日欠かさずMP3プレーヤーのヘッドフォンを耳に
差し込んではJOHNLOSの歌に聴きほれている。
日曜日あるいは土曜日に彼らのライブがあると聞けば特別な用事がない限り、
会場がどこであっても足を運ぶ。
もちろん伊勢佐木町でのライブであれば自宅から歩いていくことができる。
梅沢にはJOHNLOSがやがてメジャーになって
天高く飛び立っていってほしいという願望がある。
一般論だが、女性ファンの場合はいつまでも “自分たちのバンド” であってほしい
という独占欲が強いのではないだろうか。
性差によりそのような相違があるにせよ、
熱狂的なファンのひとりであることにはちがいない。
とくに梅沢の場合、たまたまJOHNLOSメンバーの海野哲也、桜木れおと同じ年齢に
なる二人の息子をもつ。そんなことから彼らに対する親近感が一層強くなる。
「人柄がすごくいい」
「息子と比べてしっかりしている」
そのような感心を抱きつつ、インターネットなどを駆使して
彼らの応援活動にも自然と熱が入り、至極積極的ともいえるほどである。
『JOHNLOSコレクション』――。
それはJOHNLOSの公式サイトではなく梅沢が自ら制作した “勝手応援” サイトだ。
このホームページにアクセスすると現代風アレンジ版の
“ニュー伊勢佐木町ブルース” が自動的に流れるよう設定がなされている。
もちろんJOHNLOSの歌声だ。
また画面中央にはさまざまな表情をみせる彼らの写真を掲載し、右左にはこれまでの
ライブ活動の様子を写した静止画にたどりつくボタンがいくつもセットされている。
「最初は町内会のおみこしのサイトをつくろうと思ってたんだけどねぇ……」
そういって照れ笑いを浮かべる梅沢は当初、自身の住む八幡町第二睦会など
二つの町内会からなる神輿のサークル 「宮本会」 が30周年となるので、
そのホームページを作成しようとパソコンの前に座った。
ホームページなどつくったことがない梅沢は制作方法を勉強していくうちに、
どうせつくるならJOHNLOSの応援サイトを立ち上げたい……と
途中で方針変更してしまったようだ。
梅沢はまた、このホームページ制作の延長線上で、イセザキ地区の若手集団ABYの
ブログ 『空港の街』 をリンクしたり、JOHNLOSに少しでも興味をもったり路上ライブを
見かけたりした人などのブログを見つけると、精力的にサイトのリンクを貼って
JOHNLOSをアピールしていった。
〔注〕 現在 『JOHNLOSコレクション』 というサイトはWEB上から削除
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
00:03
│Comments(0)
2015年11月06日
横浜・伊勢佐木町 物語<67>
伊勢佐木町にとって彼らはパートナーだ
「感謝の歌声」――
JOHNLOSがライブ 松坂屋の屋上 “卒業”
平成20 (2008) 年10月13日付の朝日新聞・神奈川版および湘南版には
こんな見出しが躍っていた。
その前日が屋上ライブの最終回であり、同新聞横浜総局の長野佑介記者が取材し、
翌日の紙面に記事を書いていたのだ。
彼らが新聞に掲載されるのはこれで何度目だろうか。
とにかく松坂屋でのライブはこれで終わりだ。
なんとかJOHNLOSが演奏できる場所をみつけたい――。
“ライブジプシー” になったJOHNLOSに対し、
伊勢佐木町の多くのファンが同じ気持ちを抱いていたにちがいない。
あの音が聴こえなくなったこの街は、
どこか物悲しい空気が流れているような気がしないでもなかった。
しかし伊勢佐木町でのライブ再開をもっとも願っていたのはJOHNLOS本人たちだ。
この街ではJOHNLOSのことを気にかけている人は決して少なくない。
「伊勢佐木町にとって彼らはもっとも応援していきたいアーティストのひとつだ」
協同組合伊勢佐木町商店街の事務局長である永井実もこう語る。
以前、伊勢佐木町から 「ゆず」 がブレイクし、
その昔は隣の長者町で 「クレイジーケンバンド」 も活躍していた。
このイセザキエリアで無名のミュージシャンが開花し、
やがて世の中に羽ばたいていく――こんなに名誉なことはない。
そして 「伊勢佐木町ブルース」 を知らない世代で、
なおかつ伊勢佐木町に縁もゆかりもない若いメンバーが難解なこの曲を
巧みにアレンジして “ニュー伊勢佐木町ブルース” をつくり出し、
全盛期に比べて衰退は否めないこの街を活気づけようと声をからして歌っている。
伊勢佐木町にとってJOHNLOSはパートナーのような存在だ。
さらには、音楽イベントで街を活性化させたい、この街から次代の音楽アーティストを
育てたいとねがう三~七丁目の商店街協同組合にとって、伊勢佐木町で活動する
ミュージシャンが増え、青江三奈や ゆず の次に位置づける新たなるヒーローに
JOHNLOSがなってくれればと期待する。
一・二丁目および三~七丁目の両方の商店街組織で役員を務める牛山裕子は
JOHNLOS人気をよくわかっていた。
かつて牛山ビルでのライブ活動が困難となり、
その代替場所として松坂屋の屋上で継続されることが決まったとき、
牛山ビルがある三丁目の人たちはこういって悔しがった。
「JOHNLOSを一・二丁目にとられてしまった――」
そんな当時のことを振りかえる牛山は、
同じ伊勢佐木町なんだから何丁目だろうとかまわないのに……と苦笑する。
彼女はいつもイセザキ全体のことを考えているのだ。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
23:34
│Comments(0)
2015年11月05日
横浜・伊勢佐木町 物語<66>
この街から 「伊勢佐木町ブルース」 が消えた~!?
このクリスマスライブの様子は毎日新聞の神奈川版が記事にしていた。
実は、伊勢佐木町三丁目の牛山ビルでのライブが通行人の妨げになって
中止を余儀なくされたことも5大紙のひとつである朝日新聞が取り上げていたのだ。
大手2紙に相次いで掲載されたことで彼らは一時、この街では “有名人” となっていた。
「街を歩いていると “あっ、新聞に載ってた人だ” といわれることがある」
リードボーカルの桜木れお は、おどけたような顔をして当時を振りかえる。
端正な風貌からはとても想像できないが、犯罪者として紙面に写真が載ったのでは
ないかというような表現をされたこともあったと苦笑する。
クリスマスライブが行われた場所の隣に位置する有隣堂本店から、
通りを挟んだ正面には横浜松坂屋がある。
その玄関脇から販売促進部長の石田隆はライブを眺めていた。
牛山裕子から耳打ちされたインディーズのバンドをじっくりと “査定” していたのである。
年が明けた平成19 (2007) 年1月、
松坂屋がライブ場所として屋上を提供してくれるという朗報がJOHNLOSに届いた。
朝日と毎日という全国紙2紙が矢継ぎ早に取り上げたということもあろう。
石田は快くスペースを提供したのだ。
いくら神奈川版とはいえ、全国紙に伊勢佐木町のことが話題になる。
彼らは街の広報活動にも一役買うことになったのである。
さて、メンバーと初めて対面した石田は 「ゆず」 のことが頭をよぎった。
礼儀正しく好感のもてる青年たち――ゆず に抱いた印象と変わりなかった。
それは石田の部下となる八手幡稔も同様だった。
八手幡が抱いていた、ロック系のバンドは得てして横柄で生意気だという先入観も
たちまち打ち消されてしまった。
このとき松坂屋サイドが提示した条件は、
エレベーターなど一般客用の施設は使わないことだけで、あとは一切干渉しなかった。
ところで、伝統と格式を重んずるデパートが
屋上を若手ミュージシャンにライブ場所として提供するとは、なんと寛大なことだろうか。
ゆず が店頭ライブをしていたときのことを考えても、
松坂屋は文化活動に寛容的だという印象がどうしても強くなる。
ゆずやJOHNLOSの礼儀正しい人柄が後押ししたこともあるのだろう。
ファンから何度も 「JOHNLOSに屋上を貸してくれてありがとう」 という言葉をもらった
八手幡に、彼らが愛されているバンドだということが強く伝わってきた。
街が復活再生していく過程でストリートミュージシャンの果たす役割は大きく、
松坂屋も “ゆずの再現” を期待していたのであろうか。
ニュースタイルの 「伊勢佐木町ブルース」 を奏でるJOHNLOSを、
“はまっパレ!” のフロートに乗せることを強く提案したのも松坂屋だった。
「この街によくマッチしているバンドだな……」
平成19 (2007) 年5月、伊勢佐木町チームのフロート上で 「伊勢佐木町ブルース」 を
演奏するJOHNLOSを見たとき、上司の石田とともに彼らをパレードのキャストに
推薦した八手幡には安堵の気持ちが広がった。
ところが平成20 (2008) 年10月、
横浜松坂屋が144年の長い歴史に終止符を打つことになった。
それと同時にJOHNLOSもライブする場所を失った。
この街からふたたび 「伊勢佐木町ブルース」 が消えたのだ。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
00:02
│Comments(0)
2015年11月04日
横浜・伊勢佐木町 物語<65>
定期ライブ敢行から一転し “ライブ難民” へ
かくして伊勢佐木町三丁目にある牛山ビルの階段と踊り場を借りて第二、第四日曜日の
定期ライブがスタートすることになった。
当時のメンバーは4人、リーダーの海野哲也をはじめ男前揃いということも手伝って、
回を重ねるごとに人気は高まっていった。
そして平成18 (2006) 年11月にはJOHNLOSバージョン 「伊勢佐木町ブルース」 の
インディーズ版CDを2000枚だけプレスしてリリースすると、まもなく完売した。
世の中には発売直後、あっという間に百万枚を売り上げる人気者もたしかに存在するが、
その一方で多くのアーティストは1000枚を消化するのに四苦八苦している。
ほとんど無名といってよい彼らがその倍の数を、あまり時間をかけずに “SOLD OUT!”
させるというのは、この世界では褒められていい現象だ。
「ウチと関係するアーティストはどういうわけか、みんな成功していくのよ」
いくつか所有する自社ビルの一部を彼らに提供するオーナーの牛山裕子は口元に笑みを
浮かべながらそんな “ジンクス” を語る。
牛山が過去に、この自前のビルでレストランを経営していた際、
音楽関係で下積み生活をしていた青年が、いまでは結構なポジションにいるという。
それはほんの一例のようだ。
ところで増え続ける一方の聴衆者は、やがてライブの継続を困難にさせることになる。
階段の下にある道路を歩く通行人の妨げとなり、ファンが150人ぐらいにまで及んだかと
思われるころ、ついに日ごろ迷惑を被っている人によって警察に通報される。
これ以上のライブ続行はもはや不可能となり、
JOHNLOSは牛山ビルでの定期ライブ開催を断念することになった。
それは同時に、伊勢佐木町でストリートライブをするステージを失うことを意味していた。
スタートしてからおよそ半年後のことだ。
JOHNLOSを気の毒に思ったのはもちろん、自身もいつしかファンと化していた牛山は、
彼らがここ伊勢佐木町からいなくなってしまうことが残念でならなかったのだろう。
すぐに、横浜松坂屋の販売促進部長をしていた石田隆に助けを求めた。
そのころのJOHNLOSは伊勢佐木町で知らない者はいないといってよいほどの
確固たる知名度があった。
もはや伊勢佐木町でのライブは、
この日で最後になるかと思われた平成18 (2006) 年12月23日、
彼らは商店街のクリスマスライブに出演し、有隣堂本店の横で演奏した。
寒風吹きすさぶ中、しかも師走の慌ただしいムードが漂い、
街ゆく人は足早に通り過ぎていくにもかかわらず多くの聴衆が詰めかけた。
この街ともお別れか……という感傷的な気持ちが聴く人たちにも伝わったのか、
ライブは最高にヒートアップしていた。
「お客さんの熱気がこちらにも伝わり、演奏にも気合が入った。お互いが熱を発し合い、
相乗効果でどんどん盛り上がっていったような気がした」
JOHNLOSリーダーの海野哲也はあのときのライブをこう述懐する。
これが楽しいから音楽ライブはやめられない――ひとり言のようにつぶやく
嬉々とした表情はふたたび熱を帯びていた。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
00:33
│Comments(0)
2015年11月03日
横浜・伊勢佐木町 物語<64>
こうして “ニュー伊勢佐木町ブルース” は誕生した
さっそく海野哲也はアレンジに取りかかるが、ある一点で難航をきわめた。
それはイントロ部分の “ため息” だ。どこにどう入れようか、哲也を悩ませた。
とはいえ、ため息は大切にしたい。
あれがあってこその 「伊勢佐木町ブルース」 なのである。
試行錯誤の末、ラテンとロックを融合しガットギターで演奏する、
かなり完成度の高いアレンジ曲が完成した。
彼らの音楽上におけるコンセプトを大切にし、
懐かしんで聴いても初めて聴いても親子両方が楽しめるものに仕上がった。
この 「伊勢佐木町ブルース」 は彼らのライブ活動にはもちろん、
音楽性にも大きな転機を与えた。
前述したように、この曲にはガットギターがフィーチャーされており、
それがその後の 「カナリア」 などの曲づくりにも寄与したというのだ。
往年の大ヒット曲である 「伊勢佐木町ブルース」 のアレンジを契機に、
リードギターはスペインでよく使われるアコースティックギター、
さらにスペイン独特の惹き方で演奏するという、
一般の若いバンドとは一線を画したスタイルが定着しつつあった。
平成18 (2006) 年5月24日、
衛藤弘幸はこの曲を収録したデモ用CDを手に伊勢佐木町へと赴いた。
関内駅で電車を降り、伊勢佐木町のウェルカムゲートをくぐる。
そして一丁目から五・六丁目方面に向かって歩いている途中の三丁目で、
路上ライブをするのに絶好の場所を目にした。
のちにJOHNLOSの音楽活動を支援することになる牛山ビルのひとつだ。
早速、ビルの所有者である牛山裕子にかけあった。
「伊勢佐木町ブルースを斬新にアレンジして歌っているバンドがいる。
この街を活気づけるためにも、おたくのビルのスペースをライブ用にお借りできないか」
衛藤は牛山にこう申し出た。
あまりの熱心さに牛山も心を打たれ、気がついたときには申し入れに応諾していた。
そしてまたJOHNLOSに対する衛藤のマネジメント活動もしばらくの間つづいた。
そのほぼ半月後となる6月11日の日曜日、小雨が降るなか 「伊勢佐木町ブルース」 の
アレンジ版を目玉にしてJOHNLOSの “伊勢佐木町ライブ” がスタートした。
牛山ビルでのライブ、そして毎年7月の第一日曜日に開催される
「伊勢佐木町ブルースフェスタ」 にもこの年から参加することになり、
彼らの演奏に耳を傾けるファンは徐々に増えていく。
JOHNLOSバージョンの伊勢佐木町ブルースは思っていた以上にこの街の人たちに
受け容れられたようだ。
ラテン調かつロック調のメロディは 「新鮮だ!」 という声もあれば、
その一方で 「懐かしい」 という声もあがった。
伊勢佐木町という街の特質と哲也のアレンジした “ニュー伊勢佐木町ブルース” は
どこか共通するものがあったのかもしれない。
過去に絶大な人気を博し、
長らく枯渇していたものが現代の担い手によってふたたび水を得ようとしている。
それは 「伝統と革新」 を重んずる経営と似かよっていた。
古き良き伝統は残しつつ変えるべきところは変え、新風を吹き込んでいく。
歴史ある古都・京都で成功している企業は、
この伝統と革新を併せもっていることが少なくない。
大切なのは時代と共鳴できる要素を見極める目をもつことと、
捨てること変えることへの潔さなのかもしれない。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
01:33
│Comments(0)
2015年11月02日
横浜・伊勢佐木町 物語<63>
JOHNLOSと 「伊勢佐木町ブルース」 との出会い
海野哲也の母親が幼少のころ横浜・保土ヶ谷に住んでいて、
なおかつ若いころは横浜松坂屋の前身である野澤屋に勤めていたということ以外、
JOHNLOSはヨコハマどころか、伊勢佐木町ともなんら接点はなかった。
それなのに彼らはなぜ伊勢佐木町でライブをするようになったのか――。
平成18 (2006) 年、この年の1月から毎週日曜日になるとJOHNLOSは
錦糸町駅北口の路上でストリートライブをやるようになった。
ここが彼らの拠点となったのだが、拠点といっても彼らがライブをするために、
いつもスペースが確保されているわけでない。
俗に 「ゲリラライブ」 といわれるもので毎回 “場所どり” をしなければならず、
なかなか苦労が絶えない。
また近くの交番に駐在している警官にもライブを黙認してくれるように、
自分たちの印象をよくしておかなければならない。
そんなある日、ストリートライブをしているところにひとりの男があらわれた。
「ちょっと話があるんだけど……」
JOHNLOSの4人は緊張して身を硬くした。
差し出された名刺には 『衛藤弘幸』 と記されてあった。
これまでにも衛藤は何度か彼らのライブを聴いたことがあるらしい。
衛藤はビクターエンタテインメントで音楽アーティスト関連の職務に就いていたが、
先立って退職されていた。
そこで、新たに音楽事務所を設立しようとしていて、その所属第一号のアーティストに
JOHNLOSをスカウトしようと彼らに注目していたようだ。
ここ錦糸町駅周辺はインディーズのミュージシャンが曜日に関係なく、
プロモーションライブを敢行するメッカとなっていた。
日曜日ともなると錦糸町駅北口および南口ともに自分たちの音楽を聴いてもらおうと
スペースの争奪戦が起きる。
そんなエリアだから衛藤のようにスカウト目的で街を訪れる “プロ” も少なくない。
JOHNLOSの路上ライブは午後1時にスタートし、
途中休息をとりながら3回の演奏がなされた。
その休憩時間に衛藤は彼らに対して自分の計画を打ち明けた。
それと同時に、彼らの曲調に合ったカバー曲をいくつか提案した。
それは、のちに彼らのメインレパートリーとなる 「伊勢佐木町ブルース」 をはじめとして
「勝手にしやがれ」 「22歳の別れ」 などだった。
無名のアーティストをこれから世に売り出していくには、
誰もが聴いたことのあるカバー曲が効果的となる。
そのことは長年ビクターで音楽の仕事に携わってきた衛藤には
すっかり熟知していたことなのだ。
いまでは多くの音楽ファンが知るメジャーとなったEXILEなども、
まだ世間に名を売る前はカバー曲が少なくなかったことがそれを裏づける。
さて、衛藤があげたカバー曲のうち 「伊勢佐木町ブルース」 は
JOHNLOSのメンバーもほとんど聴いたことがなかった。
1978年および1979年生まれのJOHNLOSメンバー4名は青江三奈の生声で
この曲がラジオやテレビから流れていた時代のことはまるで知らない。
この歌が大ヒットしたのは昭和43 (1968) 年だから無理もない。
そんなタイトルの歌が昔流行したことは人づてに聞いていた。
子どものころ、なにかで聴いたことがある、ため息を強く出す色気たっぷりの曲だ……
など、若い青年たちの頭の中でおぼろげな記憶が弾けた。
「自分たちのスタイルでアレンジしたら、すごくかっこよくなるかもしれない」
そんな直感めいたものを覚えたと、哲也は原曲を聴いたときのことを振りかえる。
<以下、つづく>

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at
00:22
│Comments(0)
2015年11月01日
横浜・伊勢佐木町 物語<62>
幅広い年齢層を惹きつける不思議な音楽性
音楽に年齢・性別・国境はなく、音楽は人をつなぐ――。
そんな考え方で活動をしてきたJOHNLOSが奏でる曲は無理やりジャンルで
くくってしまうのは乱暴かもしれない。
しいてジャンルをあらわすならば、
ソフトロックとラテンが融合されたスタイルといったところだろう。
ラテン調を好む彼らは、しかしそれだけだと古臭い音楽に聴こえかねないと懸念した。
そこに寺本憲之のロックギターが入ってくるだけで雰囲気がかなり違ってくる。
こうしてできあがったのが、
現在のソフトロックとラテンが巧みに融け合った音楽スタイルだ。
彼らのファンに年配層が圧倒的に多いのは、
1960年代から1970年代の歌謡曲を彷彿とさせる持ち歌が最大の理由だろう。
作詞は桜木れおが担当し、作曲とアレンジは海野哲也と憲之の他、れおも手がけるが、
歌詞もメロディも見事といってよいほどに年配者の音感をくすぐってくる。
その曲調は1960年代後半に大爆発したグループサウンズに似ている。
しかし当人たちは特別に意識したこともなければ、
いわゆる年配者向けに “レトロ調” を狙っているわけでもない。
大体がグループサウンズをまるで知らない世代なのだ。
「きっと小さい頃に流行っていた歌や親がかけていたレコードの曲などが耳に残っていて、
それが曲づくりのベースとなっているのではないだろうか」
れお はそんな解説をする。
若い青年たちがレトロな曲を奏で、年配女性にキャーキャーいわれている光景は、
さながら “ロック界の氷川きよし” である。
いまでこそ年配者が大多数を占めているが、
ファンの中心が女子中・高校生だったころもあった。
だが、活動の主体をライブハウスからストリートに変えたころ、
現在の音楽スタイルにシフトした。幅広いファン層にアピールしたかったからだ。
すると年配層をはじめとしてアラサーにアラフォー、親子づれ、団塊世代の夫婦、
80代の女性……等々、JOHNLOSファンの顔ぶれは多彩になっていった。
それはまさに彼らのいう、年齢も性別もすべてを取り払った音楽をやりたいという
JOHNLOSの願いが一歩近づいたことを物語る。
「こんなおばさんばかりじゃ嫌でしょ……!?」
時折、年配女性ファンからはこういって心配されるようだが、
これにはメンバー全員が首を横にふる。
「意識して若い世代を惹きつけようとすると僕らの音楽が崩れてしまいかねない。
それに自然体でふるまった結果が年配者を惹きつけたのであれば、
それはそれでかまわないのではないか」
れおのこの言葉にメンバーたちもうなずく。
ともすればプロモーション活動に消極的であり、押しに欠けるようにもみえてしまう。
しかし裏を返せば、それは音楽に対する思いがどこまでも純粋であるということだ。
若い女性ファンに好かれたい、戦略的に音楽活動をやっていきたい……
そんな “計算” がないからこそ幅広い年齢層から愛されるのだろう。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
01:03
│Comments(0)
2015年10月31日
横浜・伊勢佐木町 物語<61>
「ゆず」 と似て非なる 「JOHNLOS」 とは
JOHNLOSはリードボーカルの桜木れおと初代ベース奏者により
平成11 (1999) 年に結成された。
この二人に次いで初代ベース奏者の知り合いだった海野哲也と、
ライブハウスにおいてあった 「メンバー募集」 のチラシを見た寺本憲之が加わった。
その後メンバーの脱退や加入を繰り返してきたが、やがてベース奏者の湯浅敏彦が
参加することになり、しばらくはこの4人で活動していた。
当初はJOHNLOST-RICITE (ジョンロスト・リサイト) という長いバンド名だった。
だが、名前が長すぎて覚えてもらえなかったり、正しく呼んでもらえなかったり
したことから後に 「JOHNLOS」 と改名した。
またバンドが結成された12月8日はジョン・レノンの命日だったので
“JOHNをLOST” した日、すなわち 「ジョンを失った日」 ということで
「JOHNLOS」 が正式なバンド名となった。
といって、なにもビートルズのコピーバンドをはじめようとしたのではない。
偉大なる音楽家としてメンバー各位が敬愛してやまないジョン・レノンに、
哀悼の意を表して命名したのである。
ライブ場所を提供した複数の不動産オーナー牛山裕子や横浜松坂屋をはじめ、
これまでJOHNLOSに関わってきた伊勢佐木町の人々に彼らのことをたずねると、
メンバー全員の礼儀正しさと律儀さを異口同音にあげる。
ていねいな言葉遣いで接する姿は街の人たちに好感を与えた。
その面ではここ伊勢佐木町から大きく飛翔していった 「ゆず」 の再来ともいえた。
牛山は、自身が所有するビルでJOHNLOSがライブをスタートさせた
平成18 (2006) 年ころのことを思い出す。
「事務所のなかで休みなさいよ」
休憩時間に階段で待機していた彼らに牛山がこう声をかけても、
音楽勘が狂うからといって丁重に断った。
暑い日も寒い日も、決して事務所のソファーでふんぞり返るようなことはなかった。
年配者が多いこの街では、そんな謙虚さがまた人気を呼んだ要因となったのだろう。
横浜松坂屋で販売促進課長をしていた八手幡稔もまた、
同店が屋上をライブの場所としてJOHNLOSに提供していたころのことを振りかえると、
やはり彼らには良い印象しか残っていないようだった。
「とにかく人間味のある礼儀をわきまえた好青年たちだった」
だが、そんな彼らの謙虚さは、ときには消極的と映りマイナスに作用することがある。
全国に星の数ほど存在する音楽アーティストのなかで勝ち抜いていくには、
図々しいとも表現されるような積極性も必要となる。
八手幡は屋上をライブスペースとして貸していたころのことを思い出すと、
戸惑いとも悔やまれるともとれる苦笑いを浮かべた。
「もっと松坂屋を巻き込んで積極的にプロモーションすればよかったのに……」
JOHNLOSだって “伊勢佐木町のランドマーク” といわれた松坂屋で
派手なプロモーション活動を展開したかったことだろう。
でも、松坂屋に迷惑をかけてはならない、販売活動の邪魔をしてはいけない……と、
きっとそんな気持ちが強く働いていたのだ。彼らはどこまでも、やさしいのである。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
01:04
│Comments(0)
2015年10月30日
横浜・伊勢佐木町 物語<60>
この街に 「伊勢佐木町ブルース」 が帰ってきた
日曜日の昼下がり、ゆったりとした空気の流れるイセザキモールを
一丁目から五・六丁目に向かって歩いていた。
やがて三丁目に差しかかってしばらくすると、この街にたいへん馴染みのある歌が
威勢のよいサウンドに乗せてビルの谷間から聴こえてきた。
♫ あなた知ってる~ 港ヨコハマ~ 街の並木に~ 潮風吹けば~
そうっ、昭和40年代に大ヒットしたあの名曲 「伊勢佐木町ブルース」 だ。
ただ、その歌声が男性であること、そしてロック調にアレンジされていることが、
青江三奈が歌っていた原曲と異なっている。
奏でているのは平成20 (2008) 年の 「ザよこはまパレード」 、通称 “はまっパレ!”
で伊勢佐木町チームを 「準 “はまっパレ!” 大賞」 に導いたあのJOHNLOSだ。
この曲が聴こえてくると、
イセザキモールを歩いていた人々の足はその音源へと自然に向かう。
去年もおととしも “はまっパレ!” で聴いたあの斬新な 「伊勢佐木町ブルース」 を
また味わいたい、そしてフロートの上で熱唱していたJOHNLOSというバンドを
もう一度観てみたいと心が疼くのだろう。
JOHNLOSがライブをしていたのは三丁目にある 「牛山ビル」 だ。
オーナーの牛山裕子が伊勢佐木町に何棟か所有しているビルのひとつであり、
街が活気づくのであれば……と牛山は彼らに無償でライブ場所を提供する。
このビルの2階の吹き抜けになった屋外スペースがJOHNLOSのステージとなり、
毎月第1日曜日と第3日曜日に行われるライブ時はこのスペースに人が溢れかえる。
彼らのライブ活動は伊勢佐木町だけにとどまらない。
かつては錦糸町北口の路上ライブが活動の拠点だったが、
聴衆者が増えてきて南口に店舗を構えるファッションビルの 「丸井」 がしばらくの間、
店頭を貸してくれた。
その後は若手ミュージシャンのプロモーションライブを積極的に支援する
江東区のショッピングセンター 「亀戸サンストリート」 をはじめ、
ときには公演施設の名門である浅草公会堂のステージにも立つ。
ライブでは 「伊勢佐木町ブルース」 のようなカバー曲だけでなく、代表曲 「たびびと」
をはじめ 「ミラグレリア」 「華」 「カナリア」 など多くのオリジナル曲も披露する。
とりわけ伊勢佐木町でライブをするときは 「伊勢佐木町ブルース」 の演奏に熱が入る。
街の人たちも昔のままの曲ではなく、この “ニュー伊勢佐木町ブルース” によって
街がふたたび甦ることを期待しているかのようだ。
それを裏づけるように、
「伊勢佐木町ブルース」 を演奏しているときには聴衆者の数が一気に膨れ上がる。
この曲が始まると2階のフリースペースにあわてて駆け上がってくる人が少なくない。
この街にとって 「伊勢佐木町ブルース」 は今も昔も特別な存在なのである。
そしてまた、この曲のニューバージョンを自らつくり出して歌うJOHNLOSにも
街の人たちは注目する。
青江三奈や ゆず のように、衰退して久しい伊勢佐木町をふたたび盛り上げてくれる
アーティストの再来を期待しているのだった。
<以下、つづく>

Yahoo!「JOHNLOSの画像」より
Posted by やすちん at
23:49
│Comments(0)
2015年10月29日
横浜・伊勢佐木町 物語<59>
潜在力のある老舗商店街はやがて甦る~!?
商店街は全国的に衰退傾向にあるが、この街は人通りもけっこうあるし、
土曜・日曜だけではなく平日もコンスタントに売り上げている。
実際、三丁目のマクドナルドは売上成績がたいへんよく、
日本マクドナルド社の原田泳幸社長 (当時) も絶賛しているという。
また二丁目のスターバックスは、
繁盛しているモデルだということで同社幹部が大挙して視察にくるほどだ。
この2店よりもさらに奥の五丁目にある 「浜志まん」 などは立地のハンデが
あるなかで大健闘といってよい。
まだまだ伊勢佐木町にも潜在力があり、そう簡単に衰退するわけにはいかない。
この 「浜志まん」 の市村聡史や商店街組合の事務局長である永井実をはじめ、
まちおこしイベントを企画する若者たち、周辺地域とも連動して新たな街づくり構想を
練っている横浜市立大学の学生たちや建築家・都市プランナーなど
イセザキの活性化に奮闘する人々は少なくない。
そういうなかでも地元の若手有志の団体 「ABY」 など比較的若い世代の活躍が、
これからのイセザキモール再生の鍵を握っていそうである。
街は “生き物” であり、
周辺エリアの経済活動の成否などによって当該地の立地条件が大きく変わったりする。
だが、いくら立地が変化をしようとも、
老舗商店街には長い歴史とともに営々と築いてきた潜在力が備わっている。
それは前述したことでもある。
そうした潜在能力を引き出すことで、街をふたたび甦らせることができるのだ。
ところで、伊勢佐木町へのアクセスはJR関内駅の近くに位置する吉田橋側からの
ほかにも市営地下鉄・伊勢佐木長者町駅などいくつかあるが、
京浜急行線・黄金町駅からの来街ルートはこれまでほとんど未知の世界だった。
違法特殊飲食街が今なお残る黄金町が一般市民にとって、
なんとも近寄りがたい場所だったからだ。
その黄金町もクリーンな街へと変貌しつつある。
黄金町駅を降りて大通り (藤棚浦舟通り・県道81号) を南に向かい、
大岡川にかかる太田橋をわたる。
数分も歩けば左手上方に銀色のモニュメントがあらわれる。
そこが伊勢佐木町六丁目の入り口だ。
一本道であるイセザキモールの先端が関内・吉田橋側の一丁目、
そしてこちら黄金町側が六丁目になる。
ともすれば、人と自転車とで賑わいすぎている感のある一丁目側とは違った
しっとりとした雰囲気が漂うこの六丁目側の入り口は、道の両側の木々が
どこまでも真っすぐに続き、おもわず “イセブラ” をしたくなる風景が目の前に広がる。
これからの時代にふさわしい伊勢佐木町の新たな始まりを感じずにはいられない。
<以下、つづく>

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at
00:41
│Comments(0)
2015年10月28日
横浜・伊勢佐木町 物語<58>
若き世代が都市再生の原動力となっていく
明治創業の老舗がまだまだ残る三丁目から七丁目の店主は、
だいたいが二代目か三代目である。
だが、三代目、四代目へのバトンタッチが期待できないところも多いという。
全国に店舗を張りめぐらすナショナルチェーンの店にはない、
ここにだけにある唯一無二の良さが消えつつあるのはさびしい。
三代目店主はいずれも先代、先々代から受け継いだ商人としての誇りと
サービス精神をもち、儲かればなんでもありという現代気風とは一線を画している。
横浜大空襲ですべてを失ってから60年以上の歳月が流れ、
いまやわれわれの身の回りには山ほどの物があふれている。
これからは単に物を買うというのではなく、その物を扱う店主の気持ち、
そして先代から続いてきた歴史と伝統を鑑みたうえで購入にいたるという時代に
なってほしいものだ。
五丁目に 「浜志まん」 という洋菓子店がある。
95年前の明治時代に創業した当時は和菓子屋だったが、
時代の流れとともに洋菓子専門店へと業態転換をはかった。
看板商品である 「ボストンクリームパイ」 は50年くらい前からの商品であり、
実はパイではなく “ケーキ” である。
昔は甘いものが高級品で、あんこをぎゅうぎゅうに詰め込んだ最中などが高級菓子
とされたが、いまは逆に甘さ控えめのほうが人気で、このボストンは昔に比べると
糖分をほぼ半分に抑えているそうだ。
午後のお茶の時間を過ぎても、
店内のテーブル席にはコーヒーとミニボストンを楽しむお客が次々とやってくる。
ある日の昼下がり、
協同組合伊勢佐木町商店街の事務局長を務める永井実が一休みしようと顔を出した。
幼いころから伊勢佐木町の近くに住んでいる永井は、
このミニボストンが好きで、ときどき休憩時間に立ち寄る。
「子どものころ、このあたりは環境がよくないからアソコには行っちゃダメだと
親によくいわれたものだ」
ケーキをほおばりながらこう話す。
親がいう “アソコ” とは伊勢佐木町通りからちょっと脇道に入ったところ、
さらには伊勢佐木町の奥にあたる五丁目から七丁目あたりをいう。
束の間の小休止の相手をしていた浜志まん社長の市村聡史もそれに続く。
「この街は危ない! というイメージをもっているのは、実は外にいる人だけなんだよね。
ここに住んでる人たちは危ない街でないことがわかってる」
テレビで 『大都会の警察・24時……』 のような情報番組において、
「さあ事件発生だ! 伊勢佐木警察の出動だ!――」 といった映像を流したりするので、
どうしても犯罪の多い場所のように視聴者には誤解されているようだ。
実際に横浜市では伊勢佐木町のある中区よりも犯罪の多い行政区がある。
それなのに “ここ” には悪いイメージが定着していると二人は残念がる。
永井は30代になったばかり、また市村もまだ40代で、この街では若いほうだ。
これからはこういった若い世代が伊勢佐木町に “良いイメージ” を植えつけ、
街をリードしていくことになるはずである。
「私は昔のいい時代を知らないが、お客さまから必要とされる店にしたい……」
謙虚で誠実な市村はそういって日々店頭に立っている。
<以下、つづく>

五丁目「浜志まん」全景
Posted by やすちん at
00:26
│Comments(0)
2015年10月27日
横浜・伊勢佐木町 物語<57>
救世主となった 「伊勢佐木町ブルース」 の大ヒット
平成20 (2008) 年12月8日、東京・銀座の老舗ライブハウス 「銀座TACT」 にて、
ソフトロックバンドであるJOHNLOSの結成9周年記念ライブが催された。
30前後の若い男性三人組のアーティストだが、
彼らの奏でるメロディーはどこか郷愁を誘うこともあってか中高年のファンも多い。
とくにボーカルの桜木れおが熱唱する 「伊勢佐木町ブルース」 は、このグループの
海野哲也が今風に絶妙なアレンジをしつつも、原曲のもつ独特の色っぽさを残している。
その原曲となる青江三奈の 「伊勢佐木町ブルース」 が日本全国に流れたのは、
れおや哲也らが生まれるほぼ10年前のことだった。
昭和43 (1968) 年1月21日発売予定だった 「伊勢佐木町ブルース」 のテスト盤を
当時ヨコハマ最大規模のレコード店 「ヨコチク」 の社長である伊奈正明が聴いたのは、
その2カ月前となる前年の11月だった。
レコード店は師走の12月ともなると多忙を極める。
そのためレコード商組合の忘年会も11月に行われるのが慣例となっていた。
会場となる中華街の高級飯店にはレコード会社各社の営業マンが、
翌年リリースされる期待の新譜をもってくる。
そして、宴が始まる前にデモ用のドーナツ盤をプレーヤーにセットし、
レコード店の経営者たちに聴かせてアピールするのだった。
そのときだ。
ある曲が流れてきた瞬間、伊奈はドキッとして全身鳥肌がたった。
当時、一般的だったド演歌とは正反対のバタ臭いしゃれたムードに衝撃を受けた。
気がついたときにはビクターの営業マンに叫んでいた。
「この曲、なんとか年内に発売できないものか――」
年末商戦に間に合わせたいという無理を承知の直談判だった。
それから数日間、伊奈はビクターの社長にかけあった。
そしてついに念願かなって当初の予定よりおよそ1カ月も早い、
年内の営業日もあとわずかとなる12月28日の発売が実現した。
そしてレコードが入荷後、朝の開店時から夜の閉店時まで、
伊奈はヨコチクの店頭で 「伊勢佐木町ブルース」 をかけまくった。
やがて大晦日がやってきた。
街中では 「蛍の光」 や 「♫ もういくつねるとお正月~」 の童謡が流れるなか、
ここヨコチクだけは青江三奈の溜息がたっぷりと盛り込まれた 「伊勢佐木町ブルース」
が通行人にからみつくがごとく、何度も何度も繰り返されている。
異様な光景だった。
明けて正月元旦、商店街ではお琴の 「六段」 や 「春の海」、雅楽 「越天楽」 といった
正月縁起ものの音楽が当然のように奏でられていた。
だが、ヨコチクの店先だけは朝10時の営業開始とともに年末と同じく
「伊勢佐木町ブルース」 を連続演奏していた。
♫ あなた知っている 港ヨコハマ……
伊奈の熱心さに強く心を打たれたのか伊勢佐木町商店街もこの “ご当地ソング” に
注目し、青江三奈を呼んで商店街で大々的にキャンペーンを展開した。
それが功を奏したこともあって、当初はそれほど売れなかったレコードも結果的には
140万枚を売り上げる大ヒットとなり、その年のレコード大賞歌唱賞を受賞した。
この歌のおかげでやや陰りのみえた街も息を吹き返し、
「伊勢佐木町」 の名はふたたび “全国区” となった。
その勢いに乗って昭和50 (1975) 年には 「伊勢佐木町誕生百年記念祭」 を
執り行った。街をあげての15日間にわたる大騒ぎであった。
伊勢佐木町の通りは連日のごとく群衆で溢れかえり、
戦後ヨコハマ最大の祭りとなったのだ。
平成12 (2000) 年、青江三奈は膵臓ガンを患い、この世を去った。
54歳の若さだった。
その翌年、当時、商店街協同組合の宣伝委員長をしていた林博らの発案で、
伊勢佐木町四丁目に歌碑が建てられた。
林は横浜市立大学を卒業してから8年ほど大阪で働いていたのだが、
伊勢佐木町出身だ――というと、あの歌のおかげで自分の周りにいる大阪人の
ほとんどが、わが街の名前を知っていたほどである。
「飲み会になると、よくカラオケで “伊勢佐木町ブルース” を歌わされたけど、
難しい曲なので苦しかったなぁ……」
林はそういって当時を振り帰る。
この歌碑はグランドピアノを模写し、
伊勢佐木町ブルースの楽譜を刻んだパネルが埋め込まれている。
前面下には小さなボタンがあり、それを押すと青江三奈の
「伊勢佐木町ブルース」 が1分間ほど流れる仕組みになっている。
寒さも和らぎ桜も咲こうかというころ、初老の女性が上品にボタンを押した。
穏やかな青空を眺めながら、慈しむように歌碑から流れる
「伊勢佐木町ブルース」 を聴いていた。
平成になって早20年以上の歳月を要したが、
曲が流れると周辺は懐かしい昭和の空気に包まれる。
そしてまた毎年7月の第一日曜日には、
この歌碑の前で 「伊勢佐木町ブルースフェスタ」 が行われている。
<以下、つづく>

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at
00:51
│Comments(0)