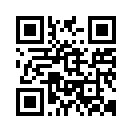2015年11月20日
横浜・伊勢佐木町 物語<81>
横浜港の歴史は 「象の鼻」 からスタートした
時計の針はそろそろ正午を指そうかというころ、
伊勢佐木町チームのフロートは山下公園西端と横浜税関、赤レンガパークを結ぶ
「山下臨港線プロムナード」 にさしかかった。
500メートルほどの遊歩道であり、
桜木町駅から港の見える丘に通じる 「開港の道」 の一部と位置づけられている。
すでに日はすっかり高くなり、
ますます明るさを増した太陽が横浜湾をキラキラと照らしている。
視界は一気に開け、情緒的な歴史建造物のセピア色に変わって、空と海の鮮やかな
ブルーが目に飛び込み、フロート上に陣取るJOHNLOSの3人は思わず唸った。
「わずかな距離を移動するだけで、こんなに景色が変わるのか……」
幼いころからヨコハマを熟知しているつもりでいたリーダーの海野哲也でさえ、
さまざまな顔をもつ街の多様性に驚きを隠せなかった。
山下臨港線プロムナードから海を眺めると、
大桟橋のつけ根から左手へ伸びる防波堤が望める。
この防波堤を上空から見ると象の鼻に似ていることから、
そのまま 「象の鼻」 という愛称がついた。
なので、この防波堤のある一帯は 「象の鼻地区」 と呼ばれている。
海岸線を見てもわかるように、このへんは横に長い浜辺が延々とつづく。
それで 「横浜」 という地名が誕生したくらいだ。
横浜港の歴史はこの象の鼻地区からスタートした。
現在、象の鼻にある防波堤の先には大桟橋の鉄橋が長く伸びているが、
開港当時は防波堤も橋もなく、砂州の中央に2本の突起状がある波止場だった。
後に “イギリス波止場” と呼ばれるこの地域から、
関内地区は外国人居留地と日本人居留地に分けられた。
元治元 (1864) 年には居留地側、ちょうどホテルニューグランドの前あたりに
東波止場 (後のフランス波止場) が築かれたが、
大正期の関東大震災で消失してしまった。
山下臨港線プロムナードの向かいには
「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」 が見える。
ここは明治27 (1894) 年の完成時には 「大さん橋埠頭」 と呼ばれ、
横浜港の玄関として活躍してきた。
現在の大桟橋は平成14 (2002) 年にリニューアルしたものだ。
ターミナルには、外国船では 「クイーンエリザベス2号」 、日本船では 「飛鳥Ⅱ」 など、
3万トンを超える豪華客船が停泊することもある。
<以下、つづく>

Yahoo!「象の鼻の画像」より
Posted by やすちん at 00:55│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |