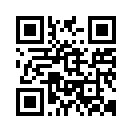2015年10月17日
横浜・伊勢佐木町 物語<47>
イセザキ隆盛の端緒は横浜開港の150年前にあった
伊勢佐木町の歴史は 「吉田橋」 が架けられた当時にさかのぼる。
もともと伊勢佐木町界隈は17世紀の半ば、
吉田勘兵衛が入り海を新田に開発したころからあった。
しかし横浜開港の安政6 (1859) 年、外国人居留地がある開港場との
交通の便が悪かったため、木製の吉田橋が架けられた。
翌年、開港場に入る人々を取り締まり、
居留地の外国人を守るため橋には関門が設けられた。
関門には常に10人ほどの役人がいて不審者の出入りを厳重にチェックした。
大門が開いているのは午前6時から午後6時まで、
その後は袖門だけを開けたが午後10時にはそちらも閉門したそうだ。
現在、吉田橋からみえるJR京浜東北線の高架橋に 「関内」 と大きく書かれてあるが、
その名前はこの150年前に置かれた関門に由来している。
外国人居留地のあった関門の内側、つまり馬車道側を 「関内」、
さまざまな人が出入りする繁華街の伊勢佐木町側を関門の外側、
つまり 「関外」 と呼ぶようになったのである。
それから10年が過ぎた明治2 (1869) 年、イギリス人ヘンリー・ブライトンの設計で、
吉田橋はわが国初となる鉄製の橋に生まれ変わる。
人々はこの橋を 「かねの橋」 と呼んで盛んに行き来するようになった。
そして2年後には関門が廃止される。 「伊勢佐木町」 が誕生したのはこのころだ。
当時の伊勢佐木町は今の一・二丁目のことで、
三~七丁目が伊勢佐木町になるのは昭和3 (1928) 年を待たねばならない。
いまでこそ人通りはさほど多くない伊勢佐木町であるが、
かつては東京の銀座や浅草をしのぐ一大繁華街であった。
明治13 (1880) 年、見世物興業取締規則により
興行場が伊勢佐木町周辺にだけ許可されたこともあって芝居小屋や寄席が集まり、
それにともなって飲食店などがつぎつぎと誕生した。
当時、全盛をきわめた芝居小屋は
現在の伊勢佐木町三丁目にあたる賑町にあった 「賑座」 に代表される。
賑座で上演された芝居に “ハンケチ芝居” と呼ばれるものがある。
町工場で、輸出用のハンケチを縁かがりする仕事に就いている若い女性たちが
通いつめたので、そう呼ばれたらしい。
彼女たちの最大の楽しみが芝居の役者たちを見ることだった。
座付役者の若手、三之助や愛之助などは人気の的だった。
<以下、つづく>

Yahoo!「伊勢佐木町の画像」より
Posted by やすちん at 19:24│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |